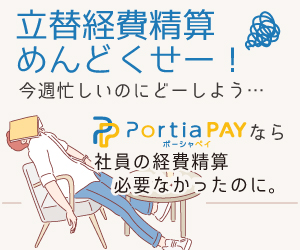2020年2月28日現在、新型コロナウィルス(coronavirus)が、中国はもとより、日本全国および世界各地で猛威を振るいはじめています。
中国の武漢市で発症した新型コロナウィルスについて、今思い起こしてみると、日本でワーワー言い始めたのは、発症当初2020年1月ぐらいですね。
日本人は、
「中国の人は大変だな~」
「日本の医療体制なら、ひとまず大丈夫らしいよ」
「震災の時にはいろいろとお世話になったから、今度はうちらが応援しよう!」
などと、どこか対岸の火事的な発想でした。
しかし、今はどうでしょうか?
私たちの想像を遥かに超えて、感染が拡大する新型コロナウィルスの影響は、ついに日常的な業務にまで暗い影を落としはじめました。
「2020年の春節の観光客が減っちゃうね~」
…と、たったそれだけの事であり、一時的な影響に過ぎないと思っていたのも束の間の出来事でした。
感染者が増すにつれ、
以下のような悲鳴が各地からちらほら聞こえはじめました。
「予定していた資材が届かない」
「納品予定の部品が届かない」
「そもそも工場自体が稼働できない」
「物流が止まっている」
「製品在庫はあるけれど、港が動いていない」
「都市や街から人がいなくなった…」
ここまで来て、やっと
「これは、日本経済にとんでもない影響が出るぞ!」
と、身に迫る戦々恐々とした実感が湧き上がったのです。
製造、物流、商社、小売などのありとあらゆる業種に影響が出始めて、私たちが日頃当たり前に使っていた生活を支える様々なものが、いかに中国に依存していたのか浮き彫りになったのが、今回の新型コロナウィルス感染拡大によるものとは、なんとも皮肉な話ですよね。
さて、現時点での新型コロナウィルス対策としては、
① 不要不急の外出や集まりは控える
② 帰宅時の手洗いの徹底
③ 外出時の咳エチケット
この程度しか、感染拡大を防ぐ手立てはないと聞きます。
いまだワクチンの開発には1年以上掛かると知り、驚きを隠せません。
今、世界は言い表しがたい不安の真っ只中に置かれていることは確かです。
そうはいうものの、
最終的に経済を回していかなければならないことを考えますと、企業・工場・事業会社は、当然、製造や取引を継続していくことを求められ、今まで通り受発注の対応をしなければなりません。
新型コロナウィルス対策には
【人と人が会わないこと】
これがなにより一番です。
しかし、人が関わらずにすべての業務を終えられる仕事には限りがあります。
今になって「あの時、全自動化、無人化、業務効率化をしておけば良かった…!」と、悔やむ企業があるかもしれませんが、それは、「働き方改革」「人手不足」が声高に叫ばれはじめた段階で取り組むべき課題だったのかもしれません。
今となってはどれだけくやもうとも“時すでに遅し”というのが現状です。
しかし、逆にとらえれば、まだ希望もあります。
今回の新型コロナウィルス感染をひとつの教訓として、今後に生かせばいいのです。
では一体
「どういう風に、受発注の流れの改善をしておけば良かったのか?」
今回のテーマはその部分に焦点を絞り、
B2B-EC.newsからの提案として
「Eコマースを上手に活用した、人の手間を省く効果効能」を説明していこうと思います。
<発注業務は1人で可能>
発注作業が1人でもできる、ということは人に会わなくても業務は遂行できる、ということに繋がります。
例えば、いつも頼んでいる物であれば、「注文履歴」を見れば、いつ、何を、どれくらいの数量で、いくらで発注したのかがすぐに分かります。
注文履歴は、Eコマースでは当たり前に備わっている機能ですので、大抵マイページで確認ができるようになっています。
発注がクラウド化されてリモートワークになったとしても、問題はありません。
発注で使うIDやパスワードを個別に発行していれば、関係部署や上席の方が、いつでも発注内容をチェックすることが可能になります。
また、Eコマースで発注が完了した場合、すぐに登録してあるメールアドレス宛に「ご注文ありがとうございます」などといった件名のメール(いわゆるサンキューメール)が届きます。
そのメールには、基本的に発注内容がすべて記載されているため、発注者本人は再度発注内容をチェックすることができますし、本人以外の関係者にもメールアドレスの転送設定をしておけば、メールで確認することができるようになります。
万が一、ここで間違った発注をしてしまったとしても、Eコマースによってはキャンセル機能がついている場合もありますので、未配送の状態であれば簡単にキャンセルすることも可能です。
ちなみに、既に発送された後に間違いに気づいた場合は…頑張ってそのEコマースの運営会社と直接交渉していただくしか方法はないと思います。そこに関しては、Eコマースだけでなく、実際の店舗で発注していたとしても、あまり変わりませんよね?
なので、総じて、EC化をすることにより、発注業務の効率は上がり、それに応じて担当人数は減らせます。
<発送業務はいつも通り>
ピッキング業務を機械化&自動化している会社も世の中にはあります。
そういう会社の場合、発注者がEコマースで発注すると同時に、その発注情報が倉庫側のシステムと連動しているので、すぐに出荷作業に取り掛かることができます。
受注処理、ピッキング、梱包、発送という一連の配送業務をシステム化することによって、人的ミス大幅に防ぎ、スピーディーに効率よく動くことができるため、倉庫からの配送業務を徹底的に省人化している企業が増えています。
そのため、導入することにより
「頼んだ商品がまだ来ない」
「発注した商品と違うものが入っている」
「注文した数量と届いた数量が合っていない」
というクライアントからのクレームもかなり減らせると思います。
(クレーム処理程、面倒で気が滅入る仕事ってないですもんね…)
<請求・改修業務はB2B請求書払いを使えば、自動で無人化>
Eコマースは受発注のシステムなので、決済機能をいかに充実させるかによって、受注側の請求業務にダイレクトに影響してきます。
よく目にするのはクレジットカード決済ですね。
クレジットカード決済を使った場合は、自動的にクレジットカード会社による請求・支払いサイクルになります。
しかし、それより便利な決済方法が世の中にはあります。
B2B請求書払いを使えば、そのサービス提供者による請求・支払いサイクルになります。
受注側(サプライヤー/販売会社)としては、
「締め日に請求書を作成し、チェックして郵送、そして支払日になったら入金確認をする」
という煩わしい一連の請求業務から解放されることになるのです。
もしも、あなたの会社がこれらの決済システムを導入していないとすれば、
もう少し具体例でお伝えすると
<月末締めの取引の場合>
- 月末で締めた受注データを、請求書発行システムを使って、請求書発行
- その請求書の内容をダブルチェックなどして、問題なければ、クライアント(バイヤー/購入会社)にメール、または印刷し郵送
- 支払日に入金確認
- 万が一、未入金が発生した場合は、未入金分を回収するために様々な関係者が督促業務を遂行
今回は例として月末締めでお伝えしましたが、これが取引先企業によって20日締めや25日締めなど、支払いサイトを変更にしている場合は、無尽蔵に人の手間ばかりが増えていきます。特に請求関連業務が一気に集中する期間はどうしても残業を増やさなければいけなかったり…といった費用面での負担も起こり得ます。
しかし、先程お伝えしたように、決済システムを導入している場合は、入金が保証されているので、督促関連の心配や苦労もなくなり、最終的に人手もいらなくなります。
注文された商品を正しく納品さえしていれば、自動的にクレジットカード会社や決済代行会社があなたに代わって請求業務を行うため、あなたの会社が請求業務でするのはただひとつ、支払期日にあなたの会社の口座に入金されるのを待つ、それだけでいいのです。
さて、いかがでしたでしょうか?
Eコマースを使うと圧倒的に省人化できるのは、ご理解いただけたのではないでしょうか。
順序は逆になってしまいましたが、上記の様に、Eコマースを上手に活用して人の手間を省くには、事前の準備がとても大切になります。
<商品登録業務がとても大切>
商品の規格は元々の業務で取り扱っているので、データはそれぞれの企業が既に保有しているものでかまいません。
EC化するために、今の時代で最も大切なのは「商品の写真」です。
「B2B-ECは、業務用だから写真なんか不要でしょ?」
という意見が少なからず出ることもありますが、B2B-EC.newsとしては、そこは口を酸っぱくして「NO!」と断言します。対面の企業間取引の打ち合わせ、面談時に、商品の企画書やサンプル、パッケージイメージを必要とするのに、何故、ECでは不要なの?おかしいですよね。
今、ネットで商品を買おうと考えているほとんどの企業担当者は、若い頃からネットショッピングに慣れ親しんでいる社員が多いです。型番をチェックしつつも、製品や部品の写真があると、より安心して発注できるのです。
発注量を増やしたり、新規顧客を獲得したいのであれば、B2B-ECであっても最低限の写真は必要だと思います。
と、今しがた「写真は絶対必要!」と強く言い切りはしましたが、逆に振り切って、
「うちは写真を1枚も掲載しない、型番のみでいい!」
という企業も、決して全否定はしません。その場合は、型番の文字を大きくして見やすくしたり、型番を間違えないように、丁寧に分かりやすくスペックを表記したり、と発注する担当者のことを考えた工夫をしているなら、それもまたひとつの販売方法だと思います。
いずれにしても、Eコマースをオープンするのも、省人化するのも、新型コロナウィルス対策をするのも、事前の準備がとても大切であるということに変わりはありません。
しかし、Eコマースはシステムだけを作れば良いものではないのです。
まず、部品や材料が調達し、製品を作り、そしてその在庫を適正に保管し発送できてこそのEコマースです。
どれが欠けてもEコマースは成功しません。
それには、様々な分野で協力してくれるパートナーを大切にしていくことが、なによりも必要だといえます。
これからEコマースを始めようと思っている皆さまのお役に少しでも立つことができれば幸いです。